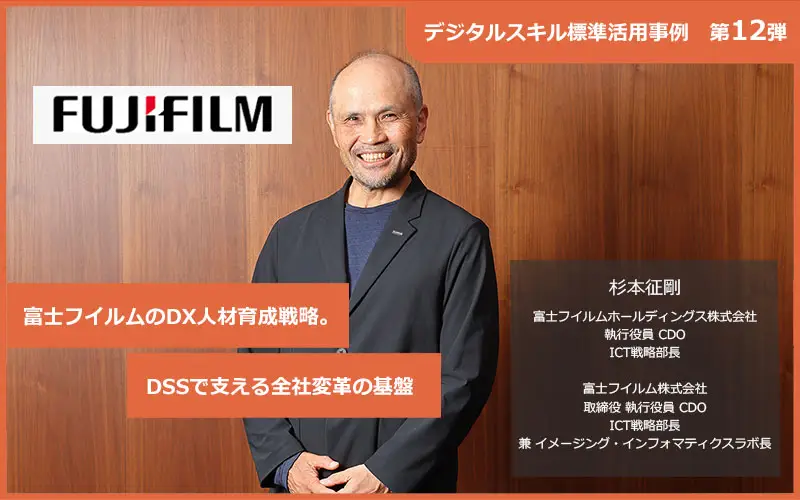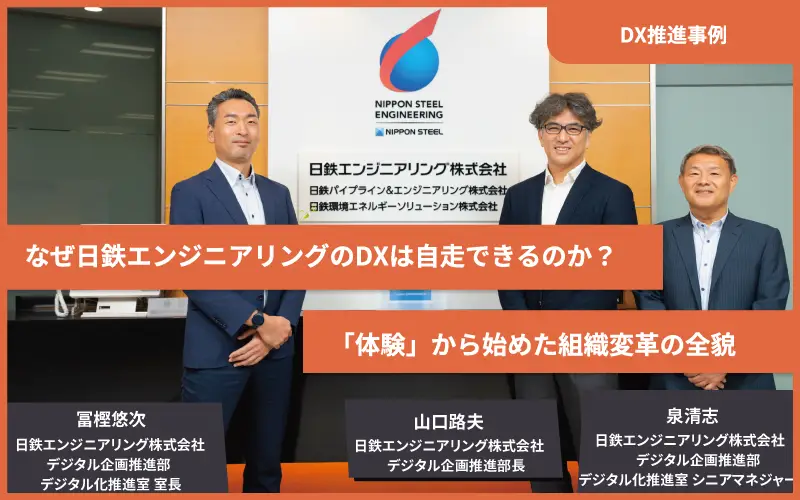物流業界のイメージを変革する ロジスティードの「D人財」と「X人財」
DX事例 人材育成
物流システム構築、情報管理、物流センター運営、輸配送など、物流業務を包括的に受託し、オペレーション水準と物流効率の向上を可能にする「3PL(サードパーティロジスティクス)」。その進化を1980年代からリードしてきたロジスティードグループでは、DXによる物流ソリューションのパッケージ化やコンサルティングサービスの進化、また社会課題である「2024年問題」への対応といった領域で新たな強みを創出するべく、「D人財」と「X人財」の育成を進めています。
業界が求める「高度物流人財」につながるDX人財
──物流業界では、どのような人材が求められているのでしょうか。
DXソリューション開発本部本部長 櫻田崇治 氏(以下:櫻田):今、「高度物流人財」と呼ばれる人財が非常に不足し、必要とされています。ドライバーの時間外労働の上限規制が厳格化されたことに伴い輸送能力が不足するなどの、いわゆる「2024年問題」は、私たち物流会社だけでなく、荷主企業にとっても共通の大きな課題となっています。そこで、さまざまなパートナーと協力しながら、いかにデジタルを駆使してロジカルに解決のための取り組みを進められるか。その動きをけん引する高度物流人財の人物像は、まさにDX人財の能力と多分に重なる部分があります。
作業効率と作業品質の向上につながるWMS(物流センター管理システム)の高度化をはじめ、当社ではこれまでにもIT、デジタルを取り入れ、取得したデータの分析・活用を積極的に推進してきました。社内にSEが在籍し、グループにソフトウエア開発企業もあり、またソリューションの創出をめざして他社との共同研究も進めるなど、DXの土台を着々と築いてきた流れがあります。

──DX人材の育成はどのように進めていますか。
DXソリューション開発本部サプライチェーンイノベーション部部長補佐 天春洋平 氏(以下:天春):2020年ごろから全社的な教育を本格化させました。それ以前に感じていた課題としては、学んだことがなかなか業務で生かせず、単発の取り組みになってしまったケースがあることでした。育成すべき人物像をしっかりと定め、そこをめざすための体系的な教育を整えていく必要がある、そんな動きの中でロールの参考とするためにデジタルスキル標準(DSS)を取り入れたのです。教育の成果を現場に落とし込んでいくことの難しさは、データサイエンティストの育成を担当する植木もこれまで強く実感してきたところだと思います。
 DXソリューション開発本部サプライチェーンイノベーション部 部長補佐 天春洋平氏(左)
DXソリューション開発本部サプライチェーンイノベーション部 部長補佐 天春洋平氏(左)
DXソリューション開発本部ロジスティクスイノベーション部 主任 植木隆雄氏(右)
DXソリューション開発本部ロジスティクスイノベーション部主任 植木隆雄 氏(以下:植木):はい。私は主に、データサイエンスの知見を現場に広く普及させ、業務改善に生かす仕組みづくりや人財育成を担当しています。データサイエンティストを育てたものの、そのスキルを「その先」にどうつなげていくかが、課題の一つとしてありました。というのも、現場によっては分析したデータを生かすための環境が十分に整っていなかったり、分析はできるが「次にどんなアクションをデザインするか」が判断できないといった状況があったからです。DSSでスキルや役割を体系立てて改めて示してもらったことで、「次にバトンを渡す相手は誰なのか」を明確に共有できるのではないかと感じています。
DSSをベースに検討することで「抜け・漏れ」を把握
──具体的にDSSをどう活用していますか。
天春:DSSの5つの人材類型を、ロジスティードグループの業務に適合させるために、カスタマイズして「8つの人財カテゴリ」に細分化しました。分類について話し合う中で、特に「ビジネス(DX)視点で技術やデータを活用した戦略を立案できる」ビジネスアーキテクトや、「ERP(SAP・Microsoft Dynamics 365)の基本知識がある」エンタープライズアーキテクトが不足していることを再認識しました。また、ITインフラ周りについては、世界的にも情報セキュリティの領域が重視されていることもあって、サイバーセキュリティエンジニアなどの育成をより強化する必要もありました。そこで、情報セキュリティ本部の田邊にもチームに加わってもらってDXを進めているというわけです。
 DXソリューション開発本部 部長 櫻田崇治氏(左)
DXソリューション開発本部 部長 櫻田崇治氏(左)
情報セキュリティ本部 担当部長 田邉裕己氏(右)
情報セキュリティ本部担当部長 田邊裕己 氏(以下:田邊):物流オペレーションの自動化やロボティクスの技術が普及し、展開できるシーンが広がり続けています。グローバルにビジネスを拡大していく上では、新しいことをどんどん打ち出していかなければ競争に勝つことはできません。
そのためには、デジタル領域を拡大し利便性を高める一方、デジタルガバナンスやコンプライアンスにおけるリスク、対応策について、ビジネスの主体であるわれわれ自身が最適解を知っておくことが大切です。その目利きが可能な人財が社内に一定数いることによって、いくつも「点」で走っているプロジェクトを、各所と関わりながらルールという「面」で管理して調和を図ることができます。情報セキュリティをはじめ、関係省庁と連携して定義づけられたDSSはわれわれにとって貴重な情報源であり、社内教育に組み込みやすいため、リスク管理が非常にやりやすくなりました。
また、DSSを基に体系化したことで人財の抜け・漏れが把握できますし、集中的に育成すべきところ、逆に育成が偏りすぎていないかといったところも確認できます。
「世界SCM競技会1位」をはじめ、成果が見え始めている
──「D人財」と「X人財」に分けたのは、どんな狙いがあるのでしょうか。
櫻田:当社グループを合わせて4万7000人ほどの人員がいる中で、IT関連部門やグループ会社含めた全体のデジタル人財は1000人ほどです。あらゆる業務でDXが欠かせないものであるとはいえ、デジタル人財以外の全員に対して一律に教育を展開してDX人財に育成していくのはハードルが高いでしょう。だからこそ、多様な人がDXに関与できるよう人財を8つのカテゴリに細分化して、それぞれの立場から推進していこうと「D人財(デジタル人財)」と「X人財(トランスフォーメーション人財)」の掛け合わせをめざす設計にしました。
 8つの人財カテゴリ(ロジスティード様提供資料)
8つの人財カテゴリ(ロジスティード様提供資料)
天春:デジタルのことをインプットする機会はたくさん用意していますが、業務に生かして結果を出していくには、トランスフォーメーションを担う人財を増やしていかなければなりません。まさにビジネスアーキテクトやロジスティクスコンサルタントを育てるために、コンサルティングや、サプライチェーン全体を見据えたソリューションへの意識を高めるための教育に注力しています。「X人財」という言葉はそれを強調し、必要性を訴求する意味合いも込めています。2024年には、サプライチェーンマネジメント(SCM)のトレーニングイベント世界SCM競技会(Global Professional Challenge 2024)において当社チームが世界第1位を獲得しました。こうした知見がSCMの新たなソリューション、サービス開発に生かされた例も増えつつあります。
──今後の取り組みについて教えてください。
植木:従来の物流現場はアナログな作業が支えていて、そこにいきなりAIやロボットを導入しても、うまく使いこなせないというギャップが生じがちです。そもそもAIができることと難しいことは何か、ロボットにはどこまでの業務を任せられるのかといったことを教育で理解してもらうことによってギャップは減らすことができる、そうした手応えを得ています。労働人口が減少していく中、これからの物流を維持していくためにもデジタルで業務を補うことが必要です。DXによってこれまでの物流業界のイメージに変革をもたらす取り組みに、教育の側面から貢献していきたいと思っています。
田邊:お客さまからは、物流のDX、サイバーセキュリティなども含めて「ロジスティードを頼れば応えてくれる」、そんな信頼感を持っていただける専門家集団でありたいと思っています。物流の現場は、おそらく一般的なイメージよりもずっとデジタルの活用が進んでおり、さらにまだまだ開拓に挑戦できる環境があります。加えて昨今では先端電子部品産業の物流など経済安全保障などとも密接に関わる業界であり、そこにデジタル活用や新たなビジネスの可能性がたくさんあります。お客さまや、これから一緒に働く次世代の人財と共に、取り組みを進めていきたいと考えています。
取材協力
関連記事
DXを推進するために必要なスキルとは 「人材」を「人財」として捉える株式会社イトーキのDX人財 育成方法
デジタル人材育成とDSS(デジタルスキル標準)活用 「DXは、最初必ず失敗します」とトヨタが言い切る真意とは?
自社の現状を見つめ、人財育成の方向性を定めるいい機会に── 帝人が取り組む「自律的DX」とは
「自分に何が足りないのか」を考えられる集団へ 大日本印刷のDXは組織を有機的に変化させていく
デジタルを共通言語に社内外のつながりを強化 大成建設の「DXアカデミー」とは?
「未来のENEOS」からバックキャストして「どんなデジタル人材が必要か」を導き出した
ゼロカーボンエネルギー社会を見据えて東京電力は「徹底的なデータ化」で変革に挑む
concept『 学んで、知って、実践する 』
DX SQUAREは、デジタルトランスフォーメーションに取り組むみなさんのためのポータルサイトです。みなさんの「学びたい!」「知りたい!」「実践したい!」のために、さまざまな情報を発信しています。
DX SQUARE とは