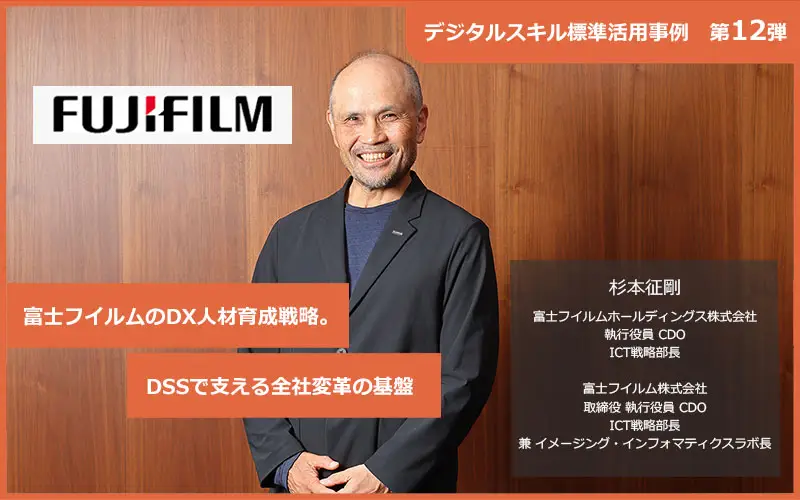DXを停滞させない「組織」に ── 前進させる「仕組み」に迫る

株式会社アシストは、1996年以来、社外のユーザー企業からメンバーを募って「ソリューション研究会」を運営。各分科会に分かれて1年間、DXや生成AIなど具体的なテーマを設け課題の解決策を研究する、企業の交流、学びの場を提供しています。
2024年度の活動において、「プレゼンテーションの部」1位を獲得した「DX推進のための組織のあり方分科会」のメンバーらが集まり、それぞれ当時の研究に対する思いなどを語り合いました。
DXの進め方を研究したいと参加
──みなさんが「ソリューション研究会」に参加した理由を教えてください。
山邉嘉寛氏(株式会社エムアンドシーシステム):当社からは毎年参加しており、社内募集がかかったので応募しました。他社の方々との交流を通して、皆さんがDXに関してどういうことを考えて進められているのか知りたいと思ったのです。
 山邉嘉寛氏(株式会社エムアンドシーシステム デジタル推進本部)
山邉嘉寛氏(株式会社エムアンドシーシステム デジタル推進本部)
中村歩登氏(株式会社エムアンドシーシステム):現在、私は新会社のマルイユナイトと兼任し、ユーザーエクスペリエンスを軸にアジャイル開発を進めています。その取り組みを通じて、組織としてどのようにDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めていくべきか、関心を持つようになりました。
そこで、DX推進をテーマに据え、1年間をかけて研究を行いたいと考えました。
 中村歩登氏(株式会社エムアンドシーシステム フィンテック第1開発本部)
中村歩登氏(株式会社エムアンドシーシステム フィンテック第1開発本部)
宮下周三氏(クリオン株式会社):当社は住宅建材を扱うメーカーで、社内にDXのノウハウがありませんでした。28歳の私が中途入社するまでは、情報システム部で一番若い社員は56歳という状況であり、人員不足のためにソリューション研究会にも積極的ではありませんでした。私が入社したタイミングで、DXを1年間学ぶのがいいだろうと上司から勧められ、この研究活動を自社のDX推進に活かす目的で参加を決めました。
 宮下周三氏(クリオン株式会社 情報システム部)
宮下周三氏(クリオン株式会社 情報システム部)
入江夕梨花氏(株式会社テプコシステムズ):私はみなさんとは異なり、アシストさんからお話をいただいて幹事として参加しました。勤務先では自社と親会社のIT・デジタル人財の育成について企画設計しています。また、デザイン思考やアジャイル開発の研修で講師をしています。
 入江夕梨花氏(株式会社テプコシステムズ ICT推進室)
入江夕梨花氏(株式会社テプコシステムズ ICT推進室)
111社の事例を抽出して検証
──この分科会のメッセージをシンプルに要約すると「DXを進めるには『仕組み』が必要で、必要な仕組みの代表格が『体制』(適切な任命)と『KPI』(適切な目標)」でしょうか。どの様な検討や分析をされたのでしょう。
宮下:DXも他の組織改革と同様、「戦略と目標」が大切です。DX推進の特徴は、ITのイメージに紐づけられて専門的に考えられてしまうこと。そして他の業務と差別化して考えないといけないのは、DX推進はすぐに実益に結びつきづらいこと。それでもモチベーションを保つにはどうしたらいいか、継続できる組織はどんな体制を整えているのかが、私たちの研究でいう「仕組み」づくりです。
中村: 我々の研究では最初に上場企業が対象のDX銘柄と中堅・中小企業が対象のDXセレクションに選定された企業111社の事例抽出を行いました。それらをまとめていったときに浮かんできたのが、「仕組み」の構築でした。そしてDX推進指標の項目の中でも大きな課題があると感じた、マインドセット・企業文化にターゲットを絞り、「体制」や「目標」をサブキーワードとして研究を進めていったんです。「仕組み」の構築というと多くのことに通じる当たり前のことにも感じられますが、研究を進める中で、我々はその当たり前ができていないことがDXの成果に大きく影響しているという気付きを得ました。
山邉:111社というのは、質より量で攻めた結果です。読み手があまり負担なく読める形にまとめることができたので、自社に似た例が見つかればいいと思います。
入江:「質よりも量」は今回のポイントかもしれませんね。対策に正解はないですし、各企業がおかれている環境は様々ですので、キーワード検索などで自社に合いそうな事例を組み合わせて試しみることができると思います。その意味で量が生きてきます。
中村:111社の事例抽出の中から各企業でできそうなものを見つけてもらえればと思います。DXは使われる文脈によってはデジタル的なツールを導入することから組織を変革することまで様々です。多くの方にとって、DXへのイメージが広くて得体のしれないように感じられることも、DX成功の難しさに繋がっていると思います。
寸劇を交えたプレゼンテーション
──成果報告会でのプレゼンに際して寸劇を織り込んでいましたね。そのターゲットは?
中村:寸劇のターゲットは経営層です。DXをやろうと決めた経営層は、なかなか成果が出ないと言う。逆に、DX推進担当者は苦労を味わっています。ありがちな構図かと思います。どうしたらうまくいくのか、経営層の共感を得ながら伝えたいと思いました。
入江:今回の寸劇は、経営と共に立場の違う社員が登場しますので、経営はもちろん、全社員がDXを自分ごととして考えるきっかけになっていると思います。

経営者のマインドを変えたアジャイル研修
――入江さんは親会社やグループ会社で研修の講師をなさっているのですね。
入江:一例をあげると、アジャイルの研修を実施しました。アジャイルと言うとシステム開発のイメージがありますが、組織としてのアジャイル思考について、まず経営層を対象にしたのです。そうしたら経営層の間でアジャイルが一種の「はやり」みたいに浸透して、今年度から管理職以上は全員受講することになりました。
――アジャイルが広がっているのですね。
入江:10年くらい前から試行錯誤してきて、ようやくの結果です。お客さまの中には「アジャイルは関係ないのに……」と言いながら渋々研修を受けに来られます。研修が終わるまでに、その思考を変えるのが私の講師としてのやりがいです。アジャイルを導入すると、ユーザ企業はベンダーに丸投げするようなことができず、すべての工程に関わらなければならないため、辛い、忙しいということになるのは免れません。しかしそれ以上に、ものづくりの成果を実感できるのがアジャイルです。少しずつ作り上げていき、そのアウトカム(価値)を実感できる魅力を伝えたいですね。
宮下:入江さんたちの戦略が緻密だったので、役員の方々も巻き込めたのだろうと思います。ある程度は力技が必要であると思いつつ、その中で計画的に進めていく姿勢は、DX推進の参考になりました。
中村:同感です。ただ研修を実施するだけではなく、長い年月をかけて、アジャイルに対する共感の輪が広がるまでのロードマップを描いていく、続けていくことが、DX推進にも必要だと感じました。
山邉:そうですね。われわれの研究会では、DXを「競争優位性を確立するために継続的に挑戦する取り組み(技術導入にとどまらず、組織変革も含む)」と定義しました。入江さんたちは10年もかけて経営層のマインドを変えてアジャイルに取り組まれています。ずっと継続して取り組んできたからこそ今があるので、あらためてDXは継続的に進めていくべきテーマと感じました。
研究成果のアピールポイントは
――あらためて、研究成果のアピールポイントをお聞かせください。
山邉:DX推進指標の中でも特に課題感の大きいマインドセット・企業文化に着目して研究しました。それらをうまく構築・改修できない企業があったときに、その方々が手がかりにできるような内容になっています。
宮下:研究対象にした111社は規模を絞らずに調べたので、どんな企業規模の方でも理解いただける成果報告書となりました。いろいろな方々に見ていただきたい内容になっていると思います。
中村:宮下さんのおっしゃる通り、企業の業種や規模を絞らずに研究したため、いろいろな方々に「DXをやっていると、こういうこともあるよね」と感じてもらえるといいですね。DXは不安を感じる場面が多いからこそ、このような事例を実施している企業がこんなにあるという意味で、成果報告書をDXの入門書として使っていただきたいです。

――1年間の研究期間では足りなかったのでは。
山邉:1年間といっても発表会があるので、その準備を差し引くと実質8~9か月の研究期間でした。やはり詰め切れなかった点もあるのは否めないところです。
宮下:分科会内で振り返りをしたとき、事例抽出はできたけれど、企業ごとの実状を当てはめると、改善の手がかりがアウトプットされるガイドブックができたらよかったと話しました。
中村:限られた期間でしたが、やれるだけのことはやったかなと感じています。我々の成果報告書は、読者の背中を押す入門書になればと思っています。
――今回の研究成果の内容を、ご自分の会社でどのように展開しようとお考えでしょうか。
宮下:社内報告会を予定しています。DX推進はITの専門的な取り組みではなく、組織改革であることを話したいと考えています。社内制度がDX推進にマッチしているか考えてもらうきっかけになればと。また部門間で連携できる仕組みがあるのかなど、「マインドセット・企業文化」を踏まえた仕組みが整っているのか、もう一度考え直す機会にしたいと思っています。今回得たDXの考え方やノウハウを、まずは管理部門に分かってもらいたいですね。他社で取り組まれているDX事例が、当社ではまだ実現されていない状況です。想像以上の差に驚かれるかもしれませんが、当社社員にはこの差に気付いてもらいたいと考えています。
中村:今回の研究で得た知識や成果は、今後も社内に継続的に共有していく予定です。 具体的には、研究の中で事例紹介した「社内イントラネットに掲載」を、DX推進を支える仕組みの一つとして実施していきたいと思います。DXの浸透には時間がかかるため、焦らず、じっくりと社内に広めていければと思います。
入江:昨年度、初めて幹事になって、最初は「DX推進のための組織のあり方」といっても答えは出ないんじゃないかと思っていました。「組織」というと漠然としたイメージになりがちですが、「仕組み」というキーワードで、最終的にはきれいにまとめることができた研究会だったと思います。彼らが真摯に研究に取り組んだことによって得られた大きな成果ですね。
DX推進のための組織のあり方分科会メンバー

| 所属企業名 | 氏名 |
|---|---|
| 株式会社エムアンドシーシステム | 中村歩登 |
| クリオン株式会社 | 宮下周三 |
| 株式会社エムアンドシーシステム | 山邉嘉寛 |
| 株式会社シー・アイ・シー | 長谷川雄一 |
| NTTドコモソリューションズ株式会社 (旧社名: NTTコムウェア株式会社) | 山中雅之 |
| 第一生命テクノクロス株式会社 | 吉村洸希 |
| 株式会社アシスト | 樺澤一稀 |
| 株式会社アシスト | 谷列樹 |
関連リンク
ソリューション研究会 2024年度分科会活動成果
講演資料と講演動画はどなたでもご覧いただけます。上記Webページのプレゼンテーションの部「第一位 DX推進のための組織のあり方 分科会(東日本)」の欄に掲載されています。
なお、一部の報告資料の閲覧にはパスワードが必要となりますので、閲覧を希望される場合はページ下部のお問い合わせボタンからアシスト事務局までお問い合わせください。
concept『 学んで、知って、実践する 』
DX SQUAREは、デジタルトランスフォーメーションに取り組むみなさんのためのポータルサイトです。みなさんの「学びたい!」「知りたい!」「実践したい!」のために、さまざまな情報を発信しています。
DX SQUARE とは